第3回新潟県自由民権シンポジウムチラシ表
第3回新潟県自由民権シンポジウムチラシ表
第3回新潟県自由民権シンポジウムチラシ裏
1 第3回自由民権シンポジウムの趣旨 今から120年前の1883(明治16)年、激化事件の一つである高田事件がおこり
ました。前年には福島・喜多方事件が、翌年には加波山事件が起きており、高田事 件がおきた1883年は全国的に自由民権運動が大きく転回しようとする時期 でもありました。高田事件とは、どういう事件でだったのでしょうか、また 当時の日本はどのような状況に置かれていたのでしょうか。このことを今回 のシンポジウムを通して、大胆に見直していこうと思います。 2 テーマ 「高田事件と近代日本」 3 開催日 2003年10月4日(土)〜5日(日) 4 場所 上越市市民プラザ 上越市土橋1914−3 ℡025−527−3611 5 日程 (1)10月4日(土) PM13:00〜16:30 ①PM13:00〜13:10 挨拶 ②PM13:10〜13:50 河西英通「高田事件―その記憶のされ方―」 ③PM14:00〜14:40 星野尚文「高田士族と高田事件」 ④PM14:50〜15:50 田崎公司「激化事件状況と高田事件―福島・喜多方事件と秩父事件の狭間で―」 ⑤PM15:50〜16:30 全体質疑 懇親会 (2)10月5日(日) AM10:00〜11:30 金谷山和親会墓地フィールドワーク(現地集合・現地解散) 6 資料展 9月20日(土)から、市立高田図書館で高田事件関係の資料を展示予定 ※4日に懇親会を予定しています。 宿泊は、各自で予約してください。 フィールドワーク参加希望者は、横山まで連絡下さい。 |
 |
「新潟日報」
2003年9月28日
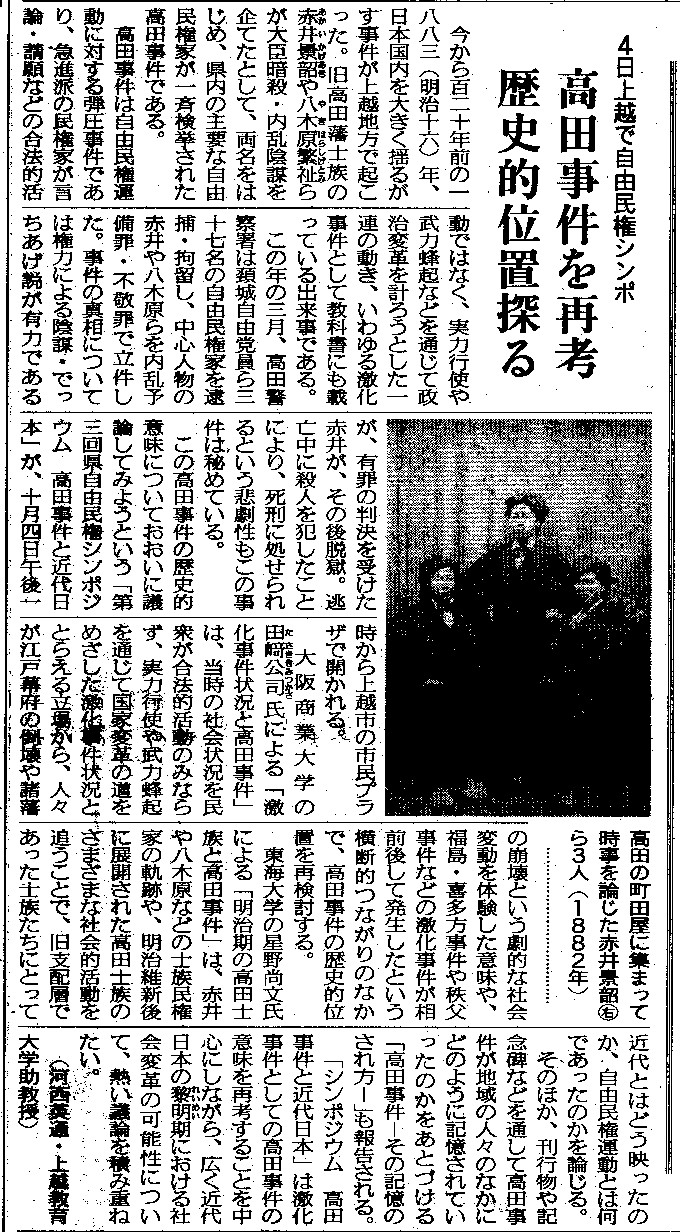 |
 |
10月4日(土)と5日(日)、第3回新潟県自由民権シンポジウム「高田事件と近代日本」が上越市で開催されました。今回はチラシのなくなり具合、また参加の申し込み状況から参加者が大幅に増加することが予想されました。実際4日のシンポジウム参加者が116名、5日のフィールドワークが65名の参加者があり、過去2回のシンポジウムを大幅にうわまわる規模になりました。これまでに行われきた上越市史編纂室主催の歴史講座も60名程の参加者であり、今回のシンポに対する市民の関心の高さをものがたっていました。左写真は、満員になった上越市民プラザです。 |
| 4日のシンポジウムの報告者と論題は、河西英通氏が「高田事件―その記憶のされ方―」、星野尚文氏が「明治期の高田士族と高田事件」、田崎公司氏が「激化事件状況と高田事件―福島・喜多方事件と秩父事件の狭間で―」でした。以下、私の感想を交えながら報告を紹介していきたいと思います。 まず河西氏の報告は、高田事件がその後どのように地域で伝えられていったのかという問題を、社会学の視点を取り入れて報告したものでした。報告で紹介された資料は、「加藤貞盟君碑」や「明治16年国事犯高田事件記念碑」などの碑文・「高田日報」や「高田新聞」などの新聞・地元発行の教育関係書・研究書・論文・史料集など多岐にわたっていました。河西氏の報告は、これまでに高田事件を取り上げた文献・資料を一同にかいして紹介した点で意味のある報告でした。また、河西氏が紹介した鉄窓会の活動は興味深いものがありました(調査は、田中茂氏が行った)。鉄窓会とは高田事件で獄に繋がれた人々の集まりで、毎年1回逮捕された3月21日に集まって懇親を深めていました。この鉄窓会の活動の一部が、報告で明らかになりました。事件関係者は、鉄窓会会合で何を思い語りあったのでしょうか。また、なぜ1937年に高田事件の碑を建立しようとしたのでしょうか。興味の尽きない問題が浮かんできます。さらに戦前の高田住民が鉄窓会や建碑をどのように見ていたのかが明らかにされれば、多様な高田事件像が提起されていくものと思われます。 |
|
 |
星野氏の報告は、近年の歴史社会学の研究成果を参考にしながら高田士族の特質と高田事件の関連を明らかにしていこうとするものでした。歴史社会学の視点から近代の士族の直面した問題を見ると、それは経済的危機と自尊心の危機であり、士族民権家は「旧来の身分意識と類似した形態で自尊心を満たすものを求める」グループに属するとのことでした。 報告では、まず西南戦争へ560名余りの多数の徴募があったことに触れました。さらに士族授産では、庄田直道らの「高田住士族就産会社」へ172名、大沼田誠らの「養蚕会社」に546名の参加があったことを明らかにしました。また北海道移住は明治19年から始まり、大正2年には81名の入植者がありました。これらのことから高田士族の動員力・組織力の高さを指摘しました。一方、士族のネットワークの場として榊神社が明治8年に創建され、また東京在住の高田士族は明治17年から懇親会を始めていました。親睦団体や育英団体の結成は遅く、育英団体「榊原慈善団」は明治42年、親睦団体「和親会」が44年に設立されました。 さてこのような高田士族の動向の中で、士族民権家はどのような動きを示したのでしょうか。報告を聞いて考えたことを述べてみましょう。まず、士族授産に重きをおいていた庄田と士族民権家八木原繁祉は対立関係にあったという事実です。このことは高田藩士族が一枚岩でないことを意味し、庄田らは多数派を形成し、八木原らは少数派でした。ここに八木原がみずからの存在を維持し活動を展開するために、鈴木昌司に代表される頸城地方の地主層と手を組む必然性があったのです。では、なぜ八木原は庄田と行動を共にしなかったのでしょうか。それは庄田らの活動は高田士族救済が第一の目的であり、八木原らは民権運動を通して国家の改革を第一の目的としたためでした。八木原と庄田の活動は、最初から相容れない性格のものだったのです。まだまだ詰めなければならない問題がありますが、星野氏の報告を聞いて八木原らの動きの一端が解明されたように思いました。 |
 |
田崎氏の報告は、明治15年の福島・喜多方事件から17年の加波山事件・秩父事件の激化事件状況のなかで、高田事件がどのような意味をもつ事件であったのかを明らかにする報告でした。1984年の自由民権百年第2回全国集会第6分科会「激化事件とは何だったのかⅡ」では、高田事件が取り上げられませんでした。田崎氏の報告は、高田事件研究の新視点を提起する報告になります。 報告ではまず高田事件の前提として福島・喜多方事件に触れ、戊辰戦争で敗れた会津藩士が高田に収監された事実に触れ、維新期の会津と高田の関わりに触れました。次に獄死した田母野秀顕の全国の民権家に与えた影響に触れ、新潟とくに高田から田母野に対する義捐金があったことを明らかにしました。田母野の死は、出版物発行や建碑、また民権家遺族の救援活動も生みだし、激化状況の気運を巻き起こすことになりました。このような激化状況の高まりの中で、17年3月赤井の脱獄が行われます。赤井の脱獄について、田崎氏は愛知の民権家内藤魯一の日誌から3月の自由党会議で武力蜂起が論じられ、これが収監中の赤井に伝わったのではないかとという事実を紹介しました。もしこれが事実であるとするならば、赤井の脱獄も激化状況に位置付けられてきます。一方東京では同じ3月に加波山事件関係者の拠点になる有一館が開館し、新潟からの醵金は高知に次ぐものでした。そして17年9月に加波山事件、10月秩父事件が勃発します。新潟でも、9月に北陸七州懇親会で星亨が拘引されます。18年7月、死刑に処せられた赤井は谷中天王寺に埋葬されます。墓碑は、田母野の墓と同型でした。また加波山事件関係者も19年9月10月死刑に処せられ、田母野・赤井と同じく谷中天王寺に埋葬されました。 田崎氏は、報告の最後に新潟の民権運動について「福島・喜多方事件以降、明瞭となった急進派の形勢と激化事件状況に新潟は、質・量ともに重要な役割を有する。赤井の脱獄・逃亡、そして処刑は、それを象徴する事件であった。さらに北陸七州懇親会が持った意味(星亨拘引と自由党の解党問題)や大阪事件への山際七司への参加を含め、新潟自由民権運動研究が究明すべき課題は山積みされているといえよう」と結びました。報告で出された点は多岐に渉っており、これからその一つ一つを慎重に解明していかなければなりません。激化事件状況の中で高田事件を見直していこうとする田崎氏の積極的な指摘は、高田事件研究が新たな段階に入ったことを示しました。 |
5日快晴のなか、金谷山和親会墓地を中心にフィールドワークが行われました。参加者が多数になったため、2班にわけて実施しました。左上写真は、「赤井景韶の墓」を説明しているところです。参加者の真剣な姿勢は、シンポジウムの時と同じでした。また規模は小さいながら、高田市立図書館で資料展示も行いました。右上写真が、資料展の一コマです。 さて、116名の参加者がありましたが、ほとんどが一般市民でした。シンポジウムに集まった人々は、定期的に行われる歴史講座のメンバーとも異なっていました。年齢的には高齢者が多かったのですが、若い方も見られました。高田事件の名前は知っているが、そのくわしい内容を知りたいという方々が今回集まったようです。このことは、自由民権シンポジウムの役割が終わっていないことを示しています。新潟のシンポジウムも来年で一応終了します。その先何をしていけばよいのか、これからの宿題です。 |
 |
4日のシンポジウム終了後、上越市で一番中華料理がおいしい店で懇親会が開かれました。左の写真はその時の模様です。今回の懇親会には、若い方々が多く集まりました。第一回のシンポジウムから参加してくれている大内さん・森田さん・野澤さん、今回東京から参加してくれた金井さん、地元からは渡邊さん・田中さんらの大学生の参加がありました。若い民権研究者がいないということが問題になっていますが、これから研究を進めていこうとする若い人たちもいます。行く手はきびしいですが、ともに協力しあい民権研究を深めていきたいと考えています。 さて毎回懇親会に出て感じるんですが、懇親会の会話は民権運動を考える上で興味深い視点を示しているような気がします。昨年のシンポに参加してくれた松崎稔氏も、「懇親会の場の方が、アルコールの力もあるのか、思いがけなく興味深い議論がなされる」と記し、二次会での議論を紹介してくれました (『自由民権』16)。今回の二次会でも、確か田崎さんから「赤井景韶が車夫を殺したかどうかわからない」という話を聞きました。車夫殺しは、自明のことと思っていた私はびっくりしました。車夫殺しが事実であるかどうかはともかく、最初から疑いもせずある事柄を信じ込む姿勢には問題があります。車夫殺し一件は、このことを示しています。新潟県自由民権シンポジウムも、あと一回になりました。第4回シンポジウムへの参加もお願いしますが、是非懇親会にもご参加ください。 |
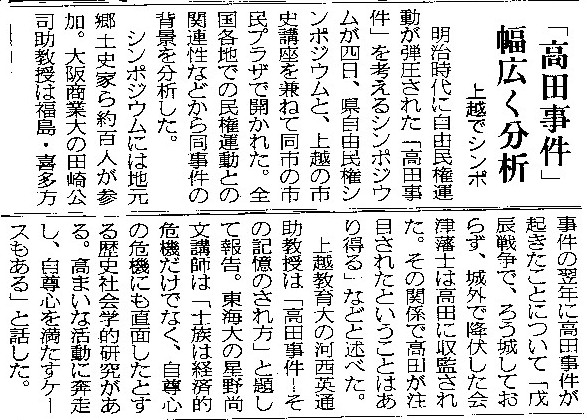 |
 |